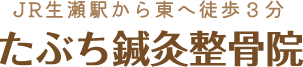こんにちは。
今日で東日本大震災から9年が経ちます。
自分自身が経験した災害ではないけれど、風化させないようにしっかりと心にとどめておきたいと思います。
1日でも早い復興を願います。
今日のブログは、震災等で避難生活をすると足がむくむと言う方が多いことを聞き、むくみについてです。
むくみとは
「むくみ」は、医学用語では「浮腫(ふしゅ)」と言います。多くの場合、病気ではありません。身体の中の水分の分布が変化した状態と考えてください。人間の身体の60%は水分でできていて、そのうち細胞の中に3分の2、細胞の外に3分の1(血液と細胞間質液※1)の割合で分布しています。血液が流れる毛細血管の壁には微小な穴があり、細胞間質液には毛細血管からしみ出した酸素や栄養素を細胞に届け、細胞の代謝によってできる二酸化炭素や老廃物を毛細血管に戻すはたらきがあります。むくみは何らかの原因によって、毛細血管からしみ出す水分量が増える、または細胞間質液から血管に戻す量が減り、細胞間質液が多くなることで起こるものです。このように、細胞と細胞間質には常に水分が存在しているため、足の場合「靴下のあとが少しつく」くらいの状態は正常です。また、細胞間質液はリンパ管にも液体を送り込んでおり、リンパ管が手術などによって詰まることがむくみの原因になる場合があります。
※1 細胞間質液: 血管外の細胞間のすきまを満たす液体のこと
むくみはなぜ起こるのか?
原因である体内水分の分布のコントロールには、①血管内の静水圧(血管内の水分量)②血管内の浸透圧③血管の透過性④リンパ管、が関与しています。その他に外的な要因として⑤長時間同じ姿勢でいること(特に下肢のむくみの場合)があげられます。それぞれについてみていきましょう。
1 血管内の静水圧の上昇
むくみは血管内の水分が多くなりすぎたとき、もしくは静脈がどこかでせき止められ、静脈血圧(血液が流れる圧力)が上昇し、血管からしみ出す水分量が増えることで起こります。水分や塩分(摂取すると水分を多く取り込む性質があるナトリウムとなって体内へ運ばれる)を摂りすぎたときにむくむのは血管内の水分量が多くなり、静水圧が上昇するためです。
原因となる病気
・心不全(心臓が血液をうまく巡回させられない)
・腎不全(腎臓がうまく水分を尿として排泄できない)
・下肢静脈瘤(下肢の静脈に水分が貯まりやすくなる)
・深部静脈血栓症(静脈の中に血栓ができる)や、子宮筋腫(腹腔内の腫瘍)で、血栓や腫瘍により血管が圧迫されたときなど
2 浸透圧の低下
血液内の栄養が少なくなると血管内に水分を保つための力(浸透圧)が低下するので、水分を血管内に保っておくことが難しくなることがあります。そのため、血管の外に水分や塩分が増え、身体がむくみます。
原因となる病気
・栄養失調(消化管の病気で血管に水分の吸収ができない)
・ネフローゼ症候群(腎臓からアルブミンが漏れてしまう)
・肝硬変(肝臓でアルブミンの生産が低下している)など
3 血管透過性が高くなる
血管透過性とは、血管と血管外の物質の出入りのことです。何らかの疾患で、血管自体が血液を保っておくことが難しくなり、水分が血管外に出てしまいむくむことがあります。
原因となる病気
・膠原病(リウマチ関連疾患)
・内分泌疾患(主に甲状腺疾患)など
4 リンパ管の閉塞
手術でリンパ節を取り除いたり、放射線治療によって、リンパの流れが停滞することで起こります。(リンパ浮腫)
5 長時間同じ姿勢でいること
長い間立ちっぱなしや座りっぱなしでいると、重力の関係で下肢に水分が貯まり、むくみの原因になります。長い間歩行した場合はあまりむくみません。これは筋肉のポンプ※2を使って血液が循環しているためです。
※2 筋肉のポンプ: 筋収縮による静脈血循環促進のこと


むくみには色々ある事がわかりますね。
下半身に流れてきた血液を心臓に戻すポンプのような働きをしている脚の筋肉を「座りっぱなし」「立ちっぱなし」では、あまり動かさないため、血流は滞り、むくみを引き起こしてしまいます。
女性は筋肉量が少ない方が多く、ただでさえポンプの力も弱いため、血流が悪くなり、それが冷えの原因にもなって、余計にむくみで悩まされることに。
このように細胞が水分をとりこめず、すき間にあふれてしまうと、水分と一緒に細胞に送られるはずの
栄養成分も、皮下脂肪や内臓脂肪へとどんどん流れてしまいます。
血流が滞ると、むくみを引き起こすだけでなく、「そんなに食べていないのに、なかなか痩せられない」
という、太りやすい体質にもなってしまいます。
むくみやすい人はどんな人?
・冷え症
・あまり歩かない、運動不足
・冷たいものをよく飲む
・アルコール・水分の取り過ぎ
・水分をあまりとらない
・塩分のとりすぎをはじめ、食事内容を気にしない
・極端な食事制限をしている
・不規則な生活
・姿勢が悪い
・長時間同じ体勢でいる
よくきく原因だと思いますが、当てはまるものはどれくらいありますか?
これ以外にも、女性は筋肉量が少ないことに加え、加齢による心臓、腎臓、肝臓の機能の低下、ホルモンバランス、自律神経の乱れなどもあります。
このよう様々な原因でカラダは血液・リンパ液の循環が悪くなります。
血流が悪いとむくみやすい
静脈やリンパ管の流れが悪くなってしまうと、水分や老廃物は回収されずに行き場を失い、皮膚の下に溜ってしまいます。これが「むくみ」となってあらわれます。
この血流を悪くする具体的な例として、長時間デスクワークをしている人は、イスに座って座面に触れている太ももからひざ裏辺りを常に圧迫して過ごしていることになります。
ずっと圧迫されている部分は血流やリンパの流れが悪くなって、余分な水分や老廃物は、静脈やリンパ菅に回収されにくくなり、体内に溜まっていく一方になり、むくんでしまいます。
立ち仕事をしている人も、カラダを圧迫されることはなくても、重力によって水分が下半身に溜まりやすくなります。
体の深い部分の筋肉(インナーマッスル)の低下もむくみの原因に!
運動不足による筋力の低下
運動量が少なく、日頃から運動不足が気になっている方、あるいは運動が嫌いだという方は体の循環機能が低下している可能性があります。循環機能が低下すると、血流やリンパの流れが悪くなったり、排泄機能が低下したりするなどし、むくみやすくなってしまうのです。
運動不足による循環機能の低下
運動不足による筋力の低下もむくみを引き起こすとされています。特に全身の筋肉の約7割を占める下半身の筋肉が低下すると、下半身がむくみやすくなるとされています。
むくみの改善のためにインナーマッスルを鍛えよう!
むくみを改善させるためには、体の内側を正しく循環させる必要があるとされています。そのためには、力こぶのような体の外側から見ることができるアウターマッスルを強化するよりも、内側のインナーマッスルを鍛えた方が効果的です。
むくみ改善は下半身を鍛えよう!
むくみで悩んでいる方の多くは足のむくみを訴える方が多いです。
なぜなら下半身は重力の影響を受けるため、余分な水分や老廃物が特に溜まりやすく、むくみやすいからです。
特に女性は筋力が男性よりも少ないため、筋力の低下で代謝が下がり、循環も悪くすることで血管やリンパ管の流れが滞ってしまいます。そこで重要な筋肉が「ふくらはぎの筋肉」です。ふくらはぎの筋肉は収縮することで、まるでポンプのように下半身を流れる血液やリンパ液を上半身に押し上げているからです。
脚のむくみは自然に治ると思いがちですが脚のむくみを放っておくとその太さになる可能性も!そしてむくみは脂肪を定着させてしまうのでセルライトの温床にもなります。むくみのケアは、早め行っておく方が良いでしょう。
むくみのある方はぜひ当院にご相談下さいね。
たぶち鍼灸整骨院では、鍼灸治療に力を入れていますので、身体の悩みを解決できるようにサポートさせていただきます。
西宮市生瀬町の《たぶち鍼灸整骨院》